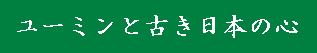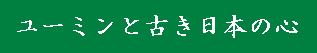| |
(1999.9.25)
|
| 秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる |
藤原敏行朝臣(古今集巻第四所収)
|
街角に立ちどまり 風を見送ったとき
季節が わかったよ |
荒井由実「生まれた街で」
|
| 作者・藤原敏行(?〜907)は36歌仙の一人で、この歌は、秋の訪れを鋭敏な感覚でとらえ表現した秀歌として、これ以降の作品にも多く引き合いに出された。意味は「秋が来たと目にははっきり見えないけれども、風の音に秋だなと自然に気づかされ、心を打たれる事だ」であり、「風を見送ったとき」に「季節が わかったよ」というユーミンの鋭い自然への感覚とも時代を越えて相通ずるものがあると、筆者は考えている。 |
|
| |
(1999.9.18)
|
| 瀬をはやみ岩にせかるゝ滝川のわれてもすゑにあわむとぞおもふ |
崇徳院(小倉百人一首所収)
|
今日の日はゆっくり 燃え尽きる 知らぬまに
離れ行く時へと 少しづつ
いつか生まれ変わり 別の人になっても
あなたを探してる 私を見つけて |
松任谷由実「Autumn
Park」
|
作者・崇徳院(第75代崇徳天皇・1119〜1164)は、悲劇の天皇である。鳥羽天皇の第一皇子として生まれ、5歳で即位したが、実権は引き続き鳥羽上皇が握り、後に若くして異母弟・近衛天皇に譲位させられた。そのため不満が重なり、1156年、鳥羽上皇が崩御すると、近衛天皇を継いでいた、やはり異母弟の後白河天皇に対して兵を上げたが敗れ、(保元の乱)讃岐の国に流されて、その地で崩御した。
和歌に熱心な天皇でもあり、百人一首の選者・藤原定家の父・藤原俊成も崇徳院の下で歌人としての生活を始めたと言われている。この歌は、「川瀬の流れが速いので、岩にせき止められる急流が二つに分かれても、最後は必ず会おうと思う。」と言う意であり、例え別れる事があっても、再び巡り合いたいという恋心の強さを示しており、このユーミンの詞の様に生まれ変わっても、と言う強い意志も言外に感じられる。
また一方で、讃岐の配所で、悲憤の内に崩御された院の都への強い思いも感じられるのである。 |
|
| |
(1999.9.11)
|
| 夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声 |
式子内親王(新古今集巻第三所収)
|
学校の坂道の下のバス停 まだ夏服着てた
いっしょに帰った9月の蝉しぐれ
哀しい なきやんでしまわないで ああ一途な面影よ
深みどりがまたひと刷毛 薄れるみたい |
松任谷由実「9月の蝉しぐれ」
|
| 作者・式子内親王(しきし(またはしょくし)ないしんのう・?〜1201)は、後白河院の第三皇女で、平安後期から鎌倉時代初期を代表する歌人の一人である。この歌は、夏の終わり、夕立の降った後、その夕立の雲もすぐに消え去り、日が傾く山に寂しく響くひぐらし(蝉の一種)の声よ、と言う意味である。夏の終わりの「ひぐらしの声」に作者の哀しみが強く託されている様であり、ユーミンのこの歌での「9月の蝉しぐれ」に託された感情と対比させてみると、非常に興味深いものがある。 |
|
| |
(1999.9.4)
|
| 限りなき思ひのままに夜も来む夢路をさへに人はとがめじ |
小野小町(古今集巻第十三所収)
|
あなたを遠くに感じる夜がなぜかあるの
言葉も何も通じない世界の果てのよう
ああ だから 心をあなたにつなげたい |
松任谷由実「Saint of Love」
|
| 作者・小野小町は、六歌仙の一人で平安女流歌人の第一人者である。歌の大意は、「限りないあなたへの思いにまかせ、せめて夢の中でもあなたに会いに行きましょう。夢の中では他の誰もとがめないでしょうから」である。思いのままにならぬ恋の苦しさを「夢」をモチーフにして描いているが、「遠くに感じ」ながらも「あなた」に心をつなげたい、ユーミンのこの歌のヒロインもほぼ同じ心境のようである。小町も今の恋に苦しんでいる時を、「世界の果てのよう」に思っているのだろう。 |
|
| |
(1999.8.28)
|
| 天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山にいでし月かも |
安倍仲麿(古今集巻第九所収)
|
| 遠い波の彼方に金色の光がある 永遠の輝きに命のかじをとろう |
荒井由実「空と海の輝きに向けて」
|
| 作者・安倍仲麿(700〜770)は、16歳で唐に留学生として渡り、玄宗皇帝に重用された。その後、751年日本への帰国の途についたが船が難破したため、唐に戻り、そのまま帰国がかなわぬまま70歳で唐で没した。この歌は一旦帰国の途についた時、唐の人々が送別の宴を開いてくれた時の歌で、夜空の美しい月を見ながら、あれは故郷・奈良の三笠の山(現在の御笠山)に出た月なのだろうか、と詠んだ歌と伝えられている。望郷の念が強く感じられるが、同時に遠い彼方に今船出して行くと言う前向きな意思も感じられる。結局帰国はかなわなかったが、ユーミン初期のこの歌のように、その時の仲麿も遠い海の彼方に命のかじをとろう、と思っていたのかも知れない。 |
|
| |
(1999.8.14)
|
| 道のべに清水流るる柳影しばしとてこそ立ちどまりつれ |
西行法師(新古今集巻第三所収)
|
| 上水沿いの小径をときおり選んだ 夏の盛りの日もそこだけ涼しくって |
松任谷由実「悲しいほどお天気」
|
| 作者・西行法師(1118〜1190)は、俗名、佐藤義清、23歳で出家し、隠者歌人として没年まで諸国を行脚した。この歌の意味は「道端に清水の流れている柳の木陰に少し休もうと思って立ちどまったのだが。(つい涼しいので長い間立ちどまってしまった)」である。夏の盛りの今の季節、ユーミンの描いた心のギャラリーの光景は、平安の隠者歌人が言葉に焼付けた夏の光景とどこかで共鳴しているようである。 |
|
| |
(1999.8.7)
|
| 五月待つ花たちばなの香をかげば昔の人の袖の香ぞする |
よみ人知らず(古今集巻第三所収)
|
窓を開けて 風を入れて 痛いくらい吸い込んだね
濡れた髪と 焼けたうなじ 痛いくらい抱きしめたね
二人きりの夕涼みは 二度と来ない季節 |
松任谷由実「夕涼み」
|
| この歌はたちばなの花の香りをかげば、昔の人の袖の香りを思い出したと言う歌で、巧みに自然と人を恋する思いを融合させており、後世、「伊勢物語」などにも多く引用されている。古今集第三の「夏の歌」所収のものであり、(五月は旧暦)湿度の低い夏の日陰のイメージが感じられ、ユーミンのこの歌における過ぎた恋を思い出させる「夏の夕暮れの涼しい風」のイメージと時を越えて相通ずるものがある。 |
|
| |